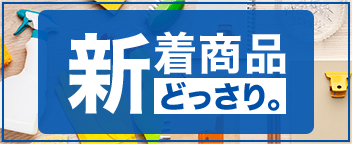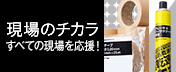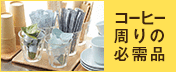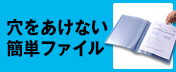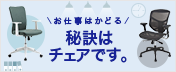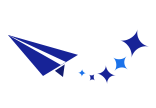更新日:2024年4月30日
養生テープとは?使い方やおすすめの選び方を紹介

引っ越し時の壁の保護や紙類の仮止め、箱の中身の目印には養生(ようじょう)テープが便利です。その汎用性の高さから、オフィスや工事現場、家庭などのさまざまなシーンで活躍しています。
この記事では、養生テープの使い方や種類、使用時の注意点について解説します。これから養生テープを使いはじめる方や、使い方のアイデアを知りたい方はぜひ参考にしてください。
養生テープとは?
養生テープとは、その名のとおり「養生」するために使用するテープのことです。
「養生」には「健康の保持・増進をはかること」「家具の運搬や塗装などをする際に周囲の壁や床を傷・汚れから保護すること」という2つの意味があり、養生テープは後者の役割を果たすアイテムといえます。
実際には保護だけに留まらず、掲示物の貼り付けや目印など、多くの目的で使用されている汎用性の高いテープです。
養生テープの特長
養生テープの最大の特長は「はがしやすさ」です。
養生テープには複数の素材がありますが、使用後にはがすることを想定して作られています。そのため、総じて他のテープよりも粘着力が弱く、一度貼っても簡単にはがすことができるのが特長です。
そのほかにも、作業性をよくするために手で切れる、はがし忘れがないように目立つ色も多く商品展開されているなどの特長もあります。
養生テープと他のテープの違い
養生テープをはじめ、「テープ」には多くの種類があります。ここからは、養生テープと混同されやすい以下の2つのテープとの違いを確認していきましょう。
- ガムテープ
- マスキングテープ
ガムテープとの違い
養生テープとガムテープの主な違いは「粘着力」にあります。養生テープよりもガムテープのほうが強い粘着力をもっているのが特長です。
一般的にガムテープと呼ばれているものは、正式には「粘着テープ」の一種です。本来のガムテープは水でぬらして接着させるタイプのことであり、実は日常生活ではあまり見かけないかもしれません。
粘着テープにはいくつかの種類があり、特にガムテープの呼び名で認識されているものは「布テープ」「クラフトテープ」「OPPテープ」の3種類です。ダンボールの梱包が代表的な使用方法で、はがれることなくフタを固定することができます。
しかし、これら3種類は粘着力が強いために貼り間違えたときに修正がしにくかったり、はがしたあとに接着剤が残ってしまったりするのが悩ましいポイントです。
一方の養生テープは、一度貼っても簡単にはがれるため、仮止めや一定期間のみ掲出するものの貼り付けに重宝します。
マスキングテープとの違い
マスキングテープとは、和紙やクレープ紙を素材とする薄いテープのことです。塗装作業の際に、塗料がはみ出して周囲が汚れないよう塗装箇所以外を保護するために使用されます。
養生テープとマスキングテープの主な違いは「素材」です。養生テープが主にポリエチレンでできているのに対し、一般的なマスキングテープは紙でできているため、マスキングテープは耐久性が低く、水に濡れると切れやすい性質を持っています。
一方、ポリエチレン製の養生テープは水をはじくため、多少濡れた程度で切れることはありません。
傷や汚れから保護をするという意味では、マスキングテープは養生テープの一種といえますが、マスキングテープのほうが幅の狭いものが多く、細かい作業に向いている傾向があります。
マスキングテープには色や柄が華やかなものも多く展開されており、近年はラッピング用や工作用としての需要が高いのも特長の1つです。
養生テープのオススメの使い方

養生テープの用途は幅広く、そのなかでもおすすめの使い方を5つ紹介します。
- 使い方① 引っ越し時の壁・家具の保護
- 使い方② 塗装作業時のはみ出し防止
- 使い方③ コード類の結束
- 使い方④ 紙類の貼り付けや仮止め
- 使い方⑤ 引き出しや箱の中身の目印
さまざまな方法で養生テープの使い勝手の良さを試してみてください。
使い方① 引っ越し時の壁・家具の保護
1つ目は、引っ越しの際に壁を傷つけないようにしたり、家具の引き出しが飛び出すのを防いだりする使い方です。
家具や家電を移動させるとき、引っ越し業者が壁や床をシートで覆うことがあります。そのシートの固定に使われるのが養生テープです。
食器棚やタンスのような扉や引き出しが付いている家具は、傾けると飛び出して破損したり、ケガをしたりする恐れもあるでしょう。危険な箇所を養生テープで固定することによって、安全に運搬できるようになります。
作業終了後にはがすときにも跡が残らず、さっと部屋を見渡せば色が目立ってはがし残しに気づけるのも使いやすいポイントです。
使い方② 塗装作業時のはみ出し防止
2つ目は、塗装作業をするときに塗料のはみ出しを防止する使い方です。
DIY初心者の方はもちろん、どんなに経験を積んだ方でも、塗装したい範囲からまったくはみ出さずに塗装するのは困難でしょう。特に端を美しい直線状に整えるのは難しいポイントです。
塗装する範囲を養生テープで囲むように貼ることで、塗料がはみ出て床や壁を汚すこともなく、端もキレイに仕上がります。
使い方③ コード類の結束
3つ目は、まとまりにくいコード類を束ねる使い方です。
コード類は絡まりやすく、いざ使用するときに取り出しにくい、何度まとめてもバラバラになって収納しにくいといった点が悩みの種でしょう。そんなときに養生テープを使用することで、まとまりにくいコード類をひとまとめにできます。
養生テープならコードを使用するときにもはがしやすく、手でも切れるので束をほどくストレスもありません。
使い方④ 紙類の貼り付けや仮止め
4つ目は、掲示物などの紙類を貼り付けや、仮止めをする使い方です。
養生テープははがすことを前提に作られているテープのため、数日後にはがすとわかっている掲示物を貼るのにぴったりのアイテムです。手ごろな大きさの紙であれば十分に固定され、はがすときの跡残りも心配いりません。
貼る位置を調整したいときの仮止めとしても使い勝手が良いでしょう。養生テープでいったん固定し、貼る位置が定まればテープをはがして正規の方法で再度固定する使い方もできます。
使い方⑤ 引き出しや箱の中身の目印
5つ目は、引き出しや箱の中身をメモして外側に貼っておく使い方です。
何がどの引き出しに入っているか判別しやすくなるため、道具や書類を探す手間がかからず作業の時短になります。会社の道具箱や家庭の引き出しなど、自分以外の人も一緒に使用する場合にもオススメの使用方法です。
目印が不要になったときには養生テープをはがせば元の状態に戻るので、外観を損ねる心配もありません。
養生テープの選び方
養生テープにはさまざまな種類があるため、いざ必要になったときにどれを選べば良いか悩むこともあるでしょう。
次の5つの観点から最適な養生テープの選び方を解説します。
- 粘着力
- 幅
- 素材
- 色・柄
- 性能
粘着力で選ぶ
養生テープの粘着力のタイプには「微粘着」「弱粘着」「中粘着」「強粘着」などがあります。
あるいは「○○N/○○mm」といった記載がされており、例えば「2.1N/100mm」なら「100mm幅の養生テープを引っ張ってはがす際に約2.1kgの重量が必要」であることを意味します。この数値が大きいほど粘着力が強いことが読み取れ、選ぶときの参考になります。
弱い力ではがしたい、跡残りなくはがしたいときは弱めの粘着力の養生テープを選び、しっかり固定したいときは強めの粘着力のものを選ぶと良いでしょう。
幅で選ぶ
養生テープの幅は50mmが一般的であるものの、15mm・25mm・100mm・150mmなどラインナップがあります。
25mm以下のような幅が狭いものは、箱の中身の目印やフタの仮止め、工業製品の一部に貼って汚れを防止する使い方がオススメです。
50mmのものは汎用性が高く、シートの固定からマスキングまで多用途に使えるので1つあると重宝します。
100mm以上の幅が広いものは、配線やシートをしっかりと固定するのに向いているタイプです。
素材で選ぶ
養生テープはポリエチレンを素材として使用していることが多く、ポリエチレンのなかでもクロスタイプとフィルムタイプがあります。
クロスタイプは糸が縦横交互に織ってあり、コシが強く強度があるため、あらゆるシーンで使える万能素材でしょう。
一方のフィルムタイプは縦方向の糸で構成されているため伸びが良く、表面がツルッとしていて油性ペンで文字が書きやすいのが特長です。
色・柄で選ぶ
養生テープの色は、緑・黄・青・赤・ピンクのようなカラータイプから白・黒・半透明の目立たないものまでバリエーションが豊富です。
養生テープは一時的に貼る(すぐにはがす)のが一般的な用途のため、はがし忘れがないように目立つ色を選ぶのが良いでしょう。
目立たせたくない場合は白、テープの下の文字が読めるようにしておきたい場合は半透明がおすすめです。屋外作業の強い日差しのなかでは、淡い色だと光が反射して見えなくなるため、黒を使用すると見つけやすいです。
単色以外にも、黄色と黒のストライプ柄や、「取扱注意」「立入禁止」などの文字が書かれた養生テープもあります。使用目的に合わせて色や柄を使い分けてみてください。
性能で選ぶ
使用シーンが明確に決まっている場合は、特別な性能のある養生テープを使うと良いでしょう。
耐熱性・耐水性・耐湿性・耐候性などに優れたタイプは、一般的なテープだとはがれやすい屋外や水周りでもはがれにくいため便利です。
屋外用のタイプなら、コンクリートやアスファルトの凸凹した面にもしっかり固定できます。両面粘着タイプならカーペットやシートの貼り付けに使い勝手がよく、外からテープが見えないため外観の美しさも損ないません。
他にも、化学物質過敏症の方に配慮した低臭タイプなど、幅広い選択肢があります。
特殊な環境で養生テープを使用する場合は、最適な性能のものを選ぶことで使い勝手も格段に向上するでしょう。
養生テープを使用するときの注意点
養生テープには注意したいポイントがあります。使用の際には気に留めておきましょう。
- 注意点① はがれて困るものには使用しない
- 注意点② 長時間の使用で跡が残ることもある
- 注意点③ 貼り付けるものの素材を選ぶ
注意点① はがれて困るものには使用しない
養生テープの最大の特長である「はがしやすさ」は、裏を返せば「簡単にはがれてしまう」ともいえます。宅配便に出すダンボールの梱包に使用すると、ちょっとしたはずみで養生テープがはがれてフタが開いてしまうことがあるので注意が必要です。
はがれやすさを念頭に置き、はがれて困るものやフタが開いて困るものには養生テープを使用しないようにしましょう。
注意点② 長期間の使用で跡が残ることもある
はがしやすさが特長の養生テープですが、長期間貼り続けると接着剤が残ってしまったり、しっかりと貼り付いて壁や床の表面を傷つけてしまったりする場合があるため、注意しましょう。
養生テープの使用は短期間にとどめ、長いあいだ貼りっぱなしにしてしまった場合にはゆっくり慎重にはがすことをおすすめします。
注意点③ 貼り付けるものの素材を選ぶ
養生テープを使用する素材によっては、はがすときに表面を傷つけてしまうことがあります。
例えばポリ塩化ビニルの面や塗装面、家具などの木材、大理石などの石材には特に注意が必要です。
これらの素材には養生テープの使用を控えるか、うっかり貼ってしまった場合は慎重にはがすようにしましょう。
まとめ
養生テープは、壁の保護やコード類の結束から引き出しの中身の目印まで、多用途に使える便利なテープです。
幅や色の展開も豊富で、耐熱性タイプや両面タイプといった性能を持つものもあるため、最適な種類を選ぶことであらゆる環境で使用できます。アイデア次第では用途が無限大に広がるでしょう。
この記事で紹介した、長時間の使用や貼り付ける素材に注意しながら養生テープを活用してみてください。
養生テープの人気売れ筋ランキング

販売価格(税抜き)
¥305~

寺岡製作所 養生テープ P-カットテープ No.4140 塗装養生用
販売価格(税抜き)
¥211~

販売価格(税抜き)
¥293~